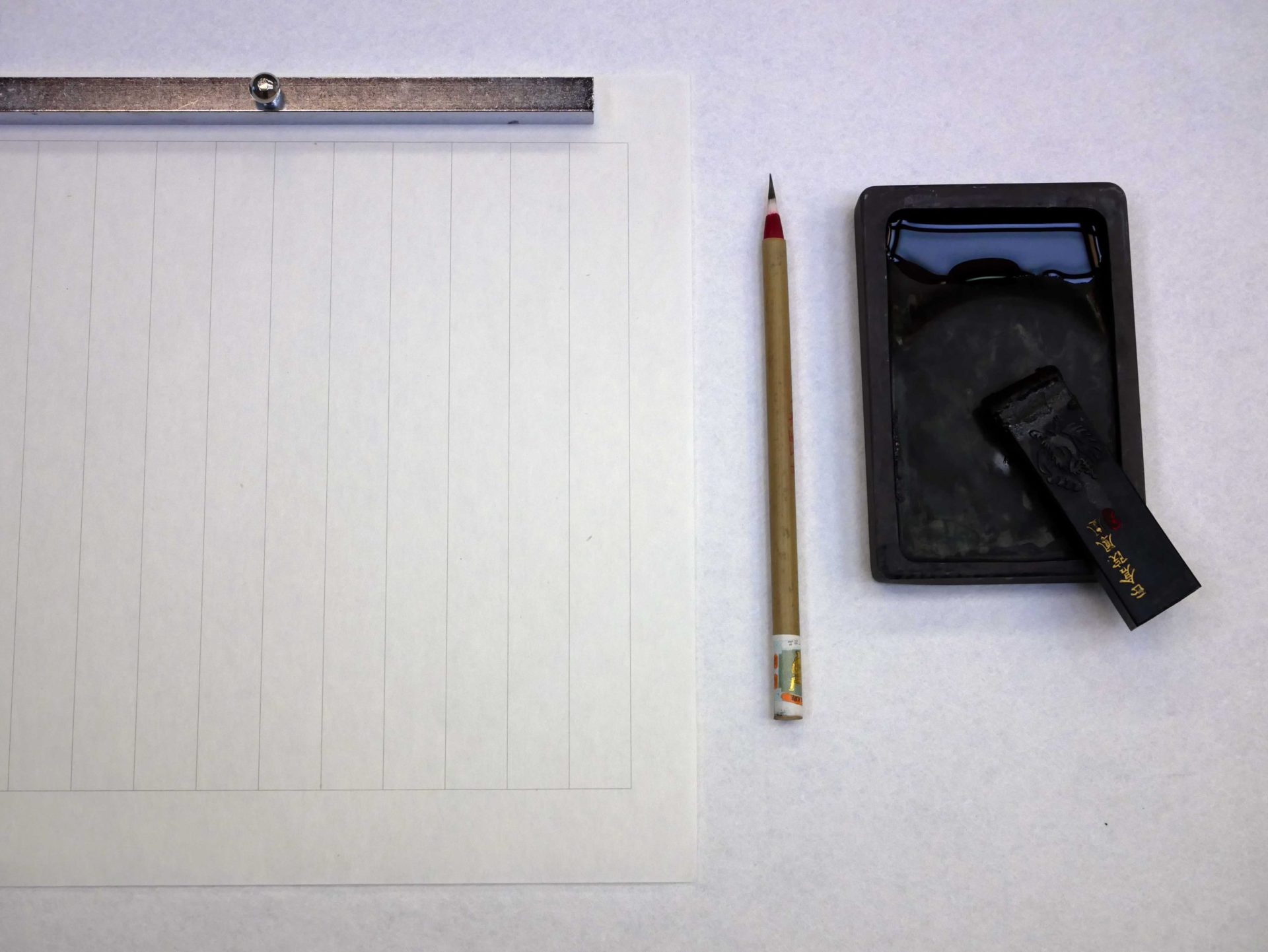3月の法話 人のために灯す火/當山第三十二世 日法上人遺稿
妙見さんの熱心なご信者の話である。
終戦後、生きていく自信を失い、死を求めて妙見様の御宝前に座ったという。そこへ偶然出て来られたのが、先代日解上人―私の師父―であった。
「死ぬのは、いつでもできる。死んだつもりで生きるんだ」、と一喝された。
ハッと我に返り、雨の中をずぶ濡れになって家路についた。それから後、本当に言われたとおり死んだつもりで一生懸命に働いて生きてきた。
「私が今日このように幸福な環境の中にあるのは、妙見様への信仰のお陰と、先代さんのお陰です。これからの余生は、妙見様へのご恩報じのため、妙見様の有り難さをたくさんの方々に伝え、一緒にお詣りに連れてきたいと思います」
この言葉通り毎月ご信者と一緒にお詣りし、私にまで感謝して下さっている。
日蓮聖人は『食物三徳御書』に「人に物をほどこせば我が身のたすけとなる。たとえば人のために火をともせば、我が前明らかになるがごとし」と示される。
人を助けるということ、人に供養するということは受けた人の感謝の念と相俟って、巡り巡って施した人の功徳となって還ってくるものである。それはたとえば、暗いところで他の人のために火を灯せば、その結果自分の前も明るくなるようなものである。
先代師父上人の為した、このご信者に対する行為が功徳となって、弟子であり息子である私に還ってきているのである。このことは師父上人もさぞかし悦んでおられることと思う。
私たちはとかく自分中心の考え方になりがちであるが、常に心して、他人のことも考えながら生きていきたいものである。
人間とは、「人と人との間」と書く。どのような人でも、自分だけでは生きていけない。他の人に生かされているのである。
してみれば、他の人を助け、また他の人のために尽くしあう心が必要であり、その心こそが「我が前を照らす火」となるのである。