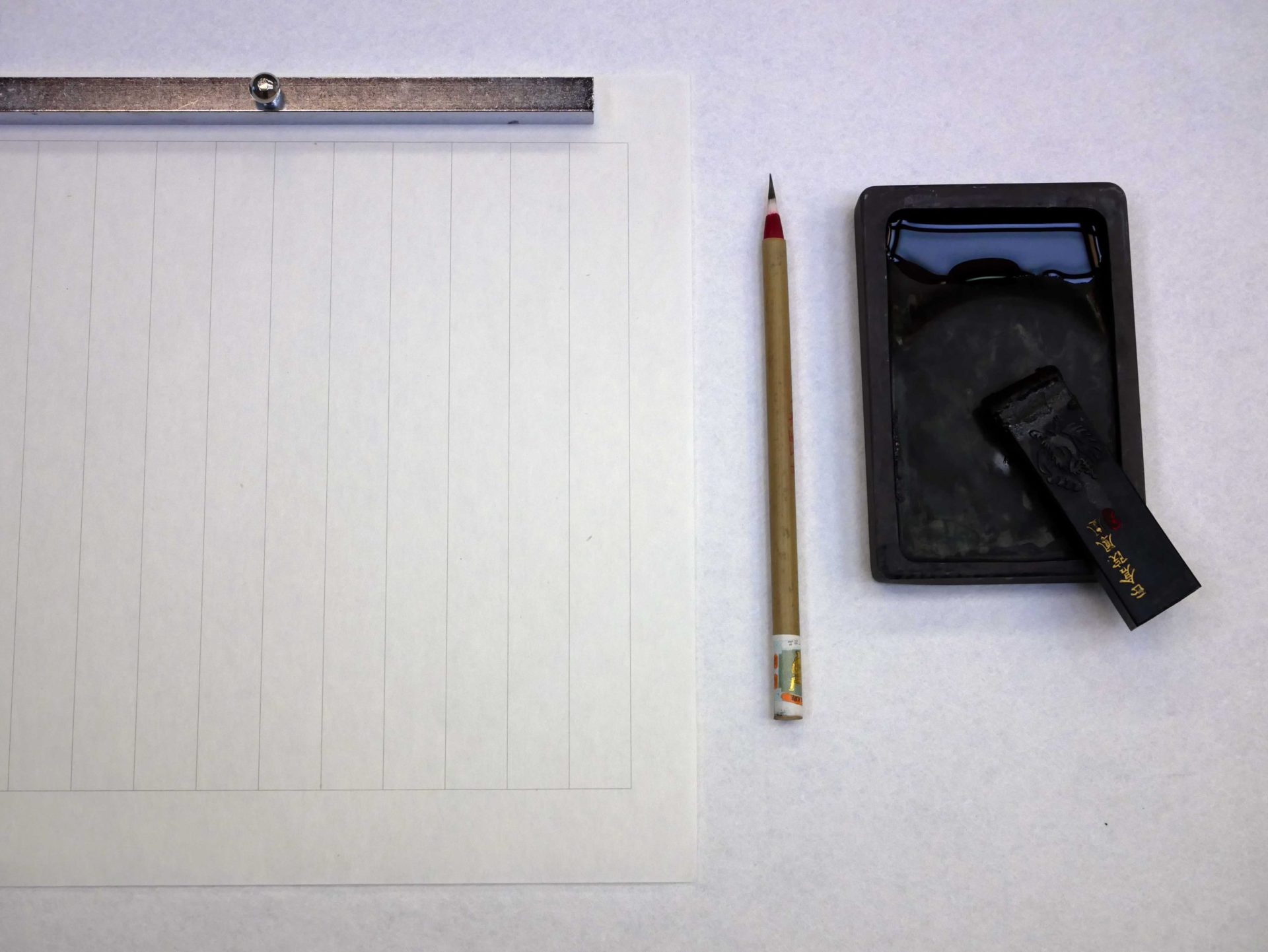1月の法話 命懸けの信仰/栗原 啓文
学生の頃宗門史の講義で衝撃を受けたことがある。それは中世の人の法華信仰についての講義だった。当時は本末制度と呼ばれる制度があり、地方の寺院の檀信徒の管理は、全てその寺院の属する本山の指示の下で行われていた。ある本山から地方の末寺にあてられたこんな指令があった。
「もし他宗の家から嫁をもらった場合、その嫁をもらい受けた夫は、必ず法華信仰に改宗させること。もしその嫁が二年以内に法華信仰に改宗しなかったなら、夫・嫁の両名ともその家から勘当させよ」
なんという衝撃的な資料だろう。法華宗の家が他宗から嫁をもらった場合、その主人は責任を持って嫁いできた者を法華宗に改宗させなければならなかったのだ。それに加えて、もし二年以内にその嫁を改宗させることができなかった場合は、二人共その家から勘当されてしまうのである。現代から考えればあまりにも非現実的だが、当時はこれが当たりだったのである。
また、こんな話もある。戦国時代最大の絵画集団の狩野家には、絵画制作に携わる絵師、その身の回りの世話をする下人に致るまで全員が法華信者でなければならないという掟が存在した。後に狩野派を脅かすまでになった長谷川派の祖、長谷川等伯も、見習いの頃は狩野派の絵師として腕を磨いていたのである。
こうして昔の人々の法華信仰を概観してみると、まさしく命懸けであったということがわかる。なにせどの宗教を信仰する家庭に生まれたかによって、その人の一生の大半が決まってしまうのだから。当時の芸術家は、作品を通して自身の信仰の表現していたのではないだろうか。現代の日本は、日本国憲法第二十条によって信教の自由が保証されている。
しかし、昔の人々のように命懸けとはいかなくてもせめて自分の拠り所としての信仰はもっていなければいけないと思う。法華経こそがその拠り所となるように広めていくことが我々日蓮宗教師の使命である。