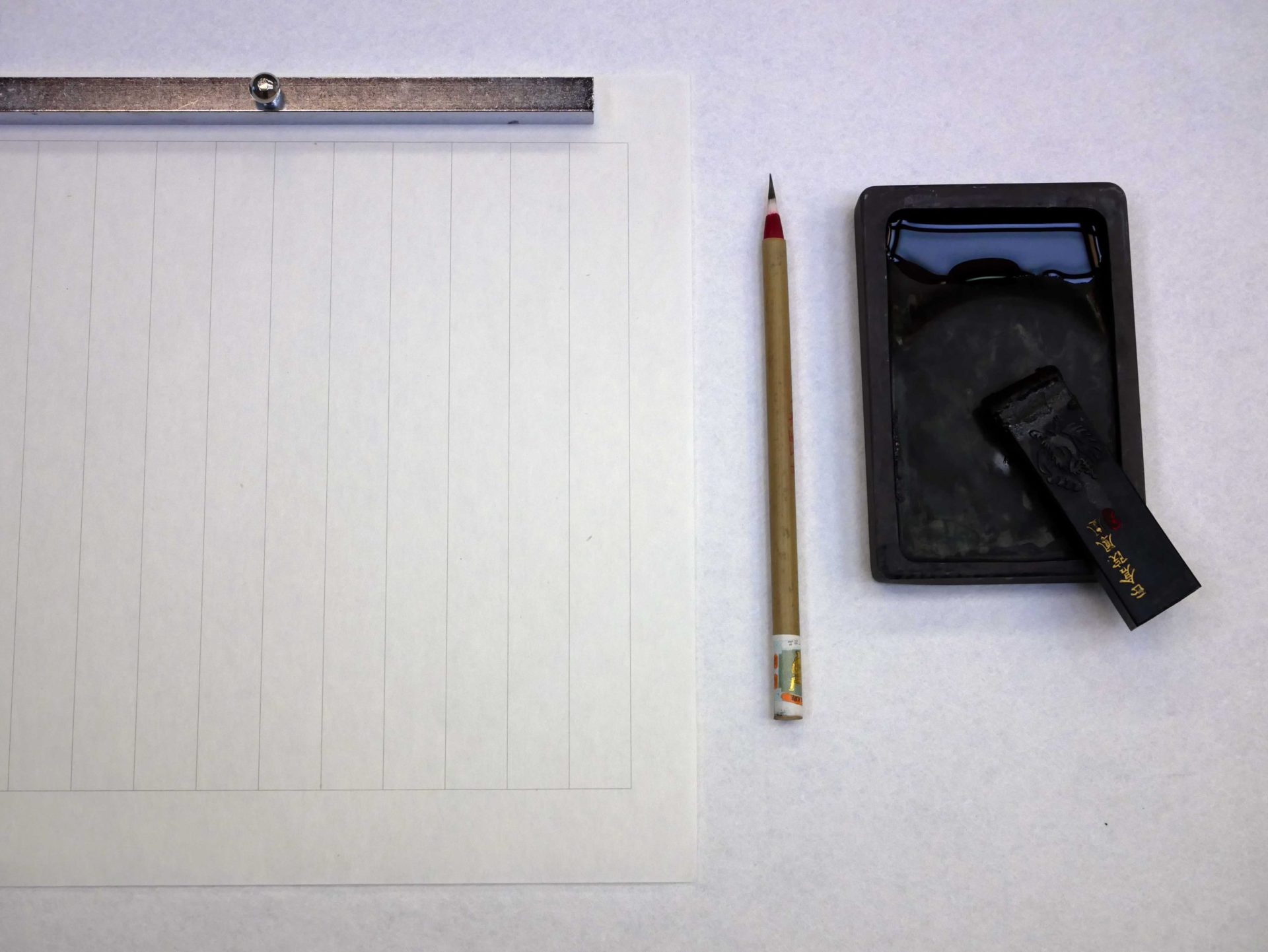1月の法話 大慈悲を感じよう/相川大輔
先日、『奇蹟がくれた数式』と題する、三十二歳で夭折したインド人の天才数学者ラマヌジャン(一八八七~一九二〇)の伝記映画を観た。
ラマヌジャンは、貧しいバラモンの家に生まれながらも、独学で数学を学び、その成果をケンブリッジ大学の数学者ハーディに書簡で送った。ハーディはラマヌジャンの天才的才能を直観的に見抜き、彼をケンブリッジ大学へ招聘する。このハーディとの出会いが、人種差別や第一次世界大戦下という困難に見舞われながらも、彼が世界の数学界で活躍する場を得る契機となる。
ラマヌジャンの才能は、よくアインシュタインの才能と比較される。アインシュタインの発見は彼が発見しなくても遅かれ誰かが発見していたであろうものであるが、ラマヌジャンの発見した公式は到底、他の人間には発見することができないものだということだ。
映画の中でハーディがラマヌジャンに、いったいどういったやり方で公式発見の着想を得るのかを聞くが、彼は「眠る時や祈る時、ナマギーリ女神が舌の上に置いていく」と答えている。彼のこの発言からも、彼の数学的な着想は、アインシュタインやハーディのような伝統的正統的学問を土台とするものとは異なり、宇宙の法則をダイレクトに感受するような直観的なものであることがわかる。
ナマギーリ女神というのは、バラモンの神であり、彼は発見した公式を神々の「贈り物」「慈悲」だと考えていたと思われる。
映画の中でも、彼は無神論者で信仰をもたないハーディに対して、「神の御心でなかったら方程式など何の意味もない」と述べている。おそらくラマヌジャンは言うなれば、久遠の仏の大慈悲の御心を、神々を通じて感じていたのだろう。
新年を迎えて、ラマヌジャンのように大発見とまではいかないまでも、日常の生活の中で、久遠の仏の大慈悲を感じて生きていくぞという思いを新たにしたのであった。